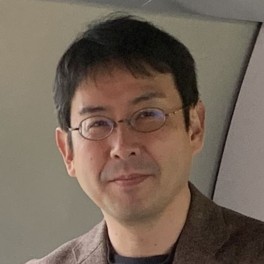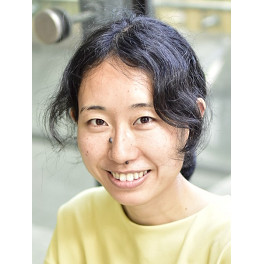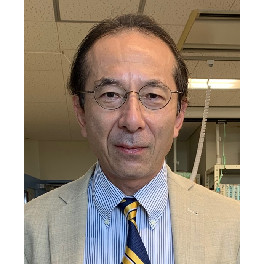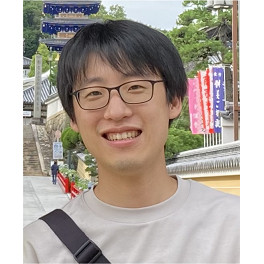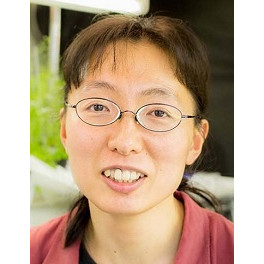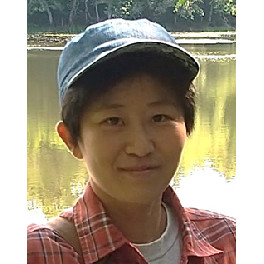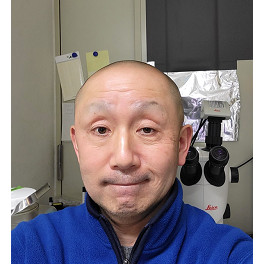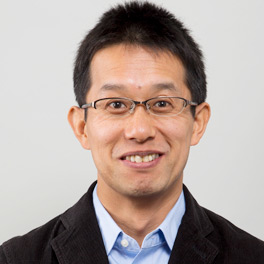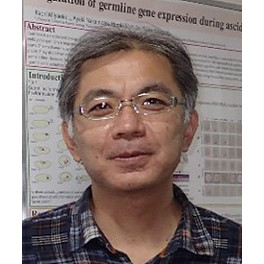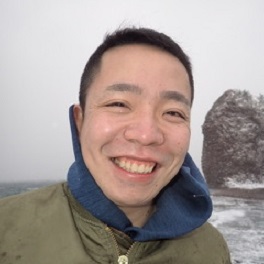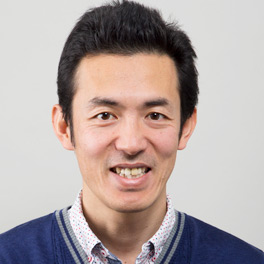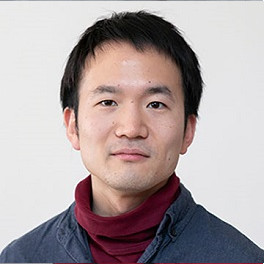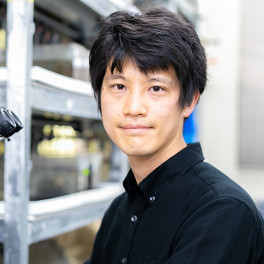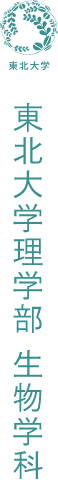東北大学理学部 生物学科
研究分野一覧
(各分野の詳細は分野名をクリックしてください)
-
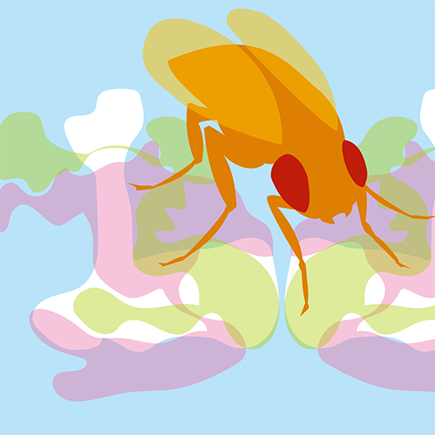
- 神経行動
- 谷本拓 教授小金澤雅之 准教授黄子庭 助教学習・記憶の脳神経基盤を解き明かす
-
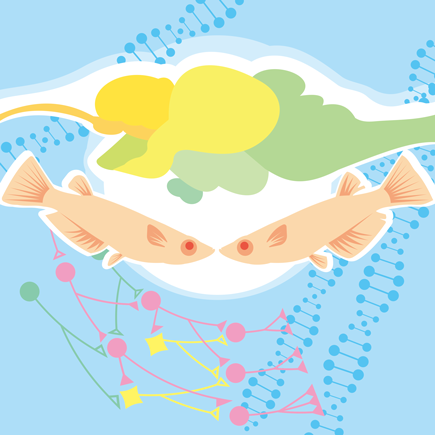
- 分子行動
- 竹内秀明 教授梶山十和子 助教社会適応を可能にする脳の動作原理の解明を目指す
-
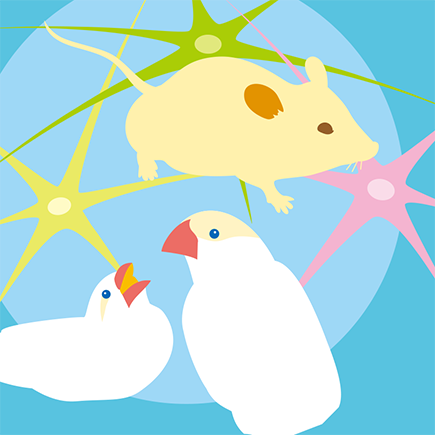
- 脳機能発達
- 安部健太郎 教授青木 祥 助教脳が変わる機構を明らかにし、その制御を目指す
-
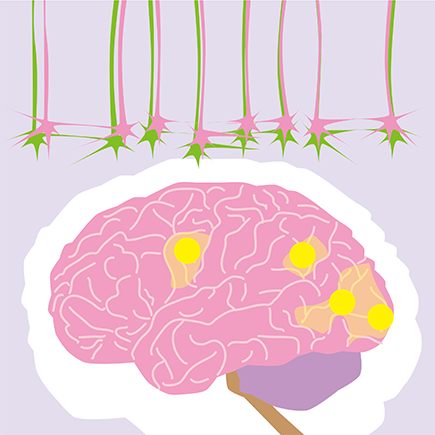
- 脳神経システム
- 筒井健一郎 教授大原慎也 准教授脳の機能的構造を理解する
-
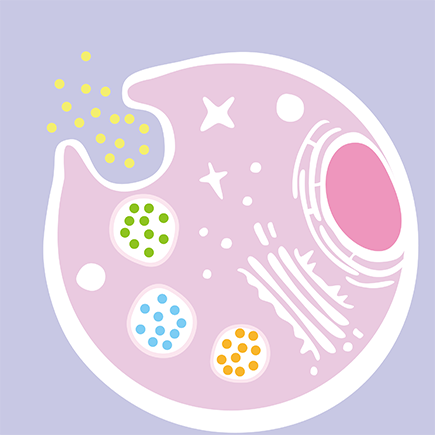
- 膜輸送機構解析
- 福田光則 教授笠原敦子 助教細胞内で起こる様々な小胞輸送の仕組みを分子レベルで理解する
-
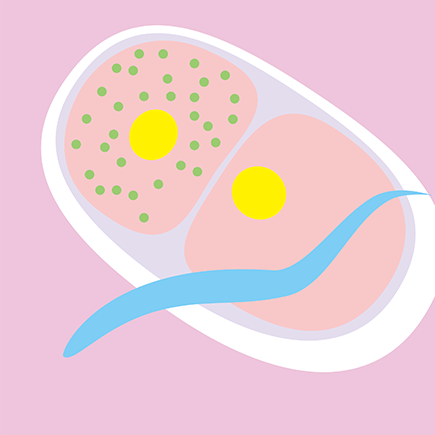
- 発生ダイナミクス
- 杉本亜砂子 教授春田奈美 助教受精卵から動物個体ができるまでを解き明かす
-

- 細胞小器官疾患学
- 田口友彦 教授細胞小器官の未知なる機能を探る
-
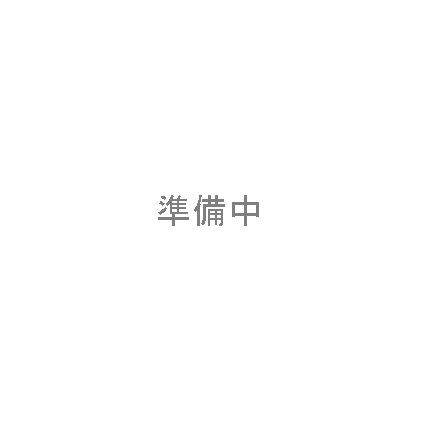
- 神経細胞生物学
- 丹羽伸介 准教授モータータンパク質と細胞骨格による細胞の形づくりを理解する
-

- 植物繁殖生態
- 酒井聡樹 准教授植物の適応戦略を解き明かす
-
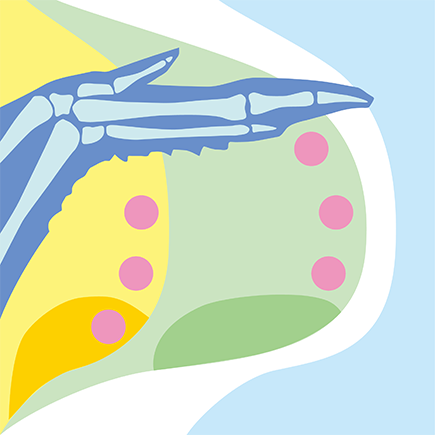
- 動物発生
- 田村宏治 教授上坂将弘 助教脊椎動物の付属肢を題材とした動物の形づくりのメカニズムを読み解く
-
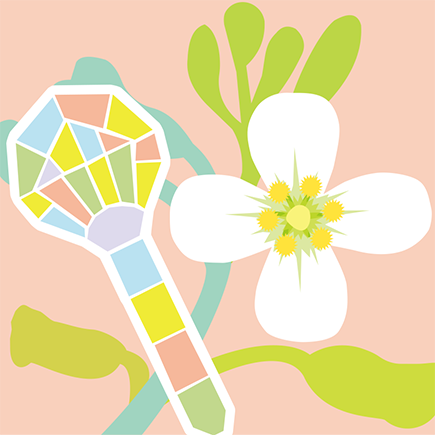
- 植物細胞動態
- 植田美那子 教授木全祐資 助教植物の形づくりのしくみを細胞内部の変化から解き明かす
-

- 流域生態
- 宇野裕美 准教授牧野渡 助教自然本来の森・川・海を含む生態系の成り立ちを明らかにする
-

- 機能生態
- 彦坂幸毅 教授冨松元 助教生物のなぜ:HowとWhyを探る
-

- マクロ生態
- Jamie M. Kass 准教授Everton Miranda 助教竹重志織 助教生物多様性の大規模な時空間パターンとその地球変動による影響を理解する
-
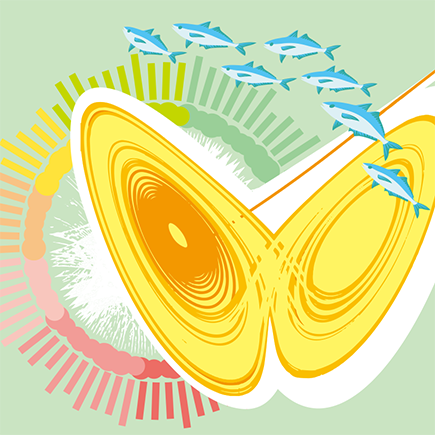
- 統合生態
- 近藤倫生 教授太田宏(高教セ) 助教川津一隆 助教生態系を特徴付ける多様性・複雑性・適応進化を統合的に理解する
-
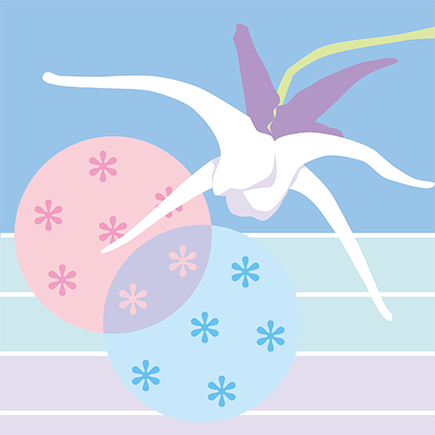
- 植物進化多様性
- 牧雅之 教授(植物園)大山幹成 助教(植物園)伊東拓朗 助教(植物園)植物の多様性に多角的にアプローチする
-
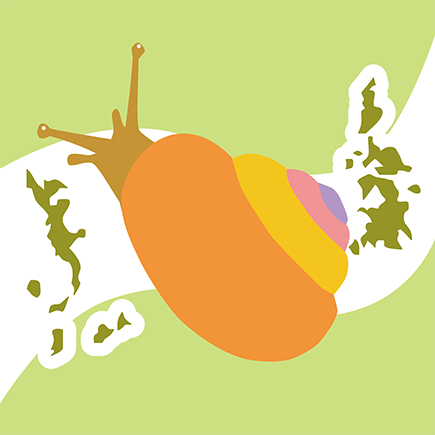
- 生物多様性保全
- 千葉聡 教授(東北アジア)木村一貴 助教(東北アジア)生態、進化研究から、保全を目指す
-

- 海洋生物多様性
- 熊野岳 教授(浅虫)近藤倫生 教授(兼任)美濃川拓哉 准教授(浅虫)岩﨑藍子 助教(浅虫)森田俊平 助教(浅虫)海洋生物の多様性を発生学的、生態学的に理解する
-
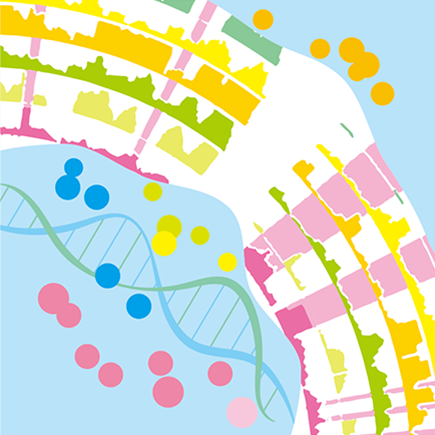
- 進化ゲノミクス
- 牧野能士 教授市之瀬敏晴 准教授(学際フロンティア)横山隆亮 講師別所-上原 奏子 助教別所-上原 学 助教(学際フロンティア)生物の進化をゲノム情報で紐解く