Topics in 2015
過去のトピックス:2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
2015.12.19
福島で行われた東北植物学会大会に今年も研究室総出で参加してきました。終了後は鍾乳洞を見学。
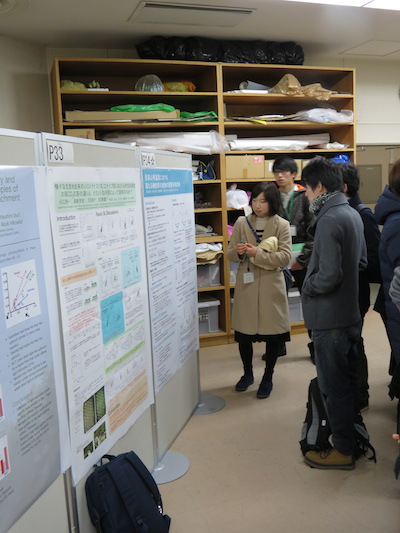 _
_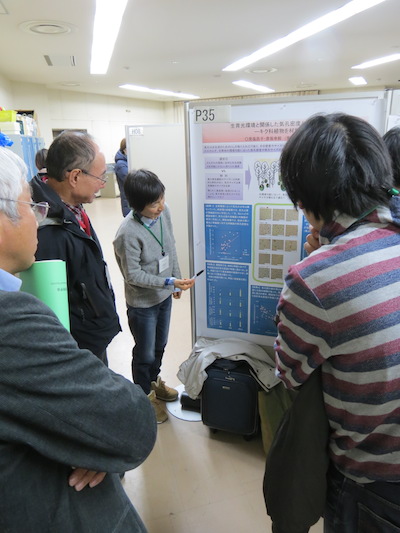
 _
_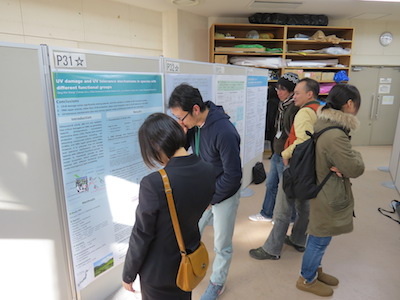
 _
_
2015.11.26
ニールスアンテン教授を迎えてミニシンポを開催しました。国環研の伊藤昭彦さん、静岡大の飯尾淳弘さん、東大の宮沢佳恵さん、名誉教授の廣瀬忠樹さんなど、アンテンさんと共同研究をしてきた研究者にも発表いただき、(予想外に)活気のあるシンポとなりました。ご参加いただいた方々には感謝申し上げます。
 _
_
 _
_
 _
_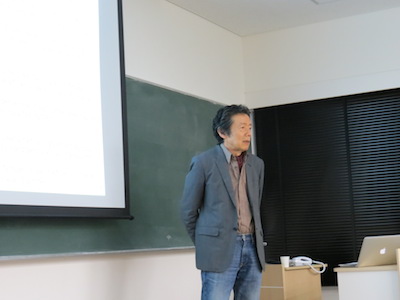
2015.11.13
ニールスアンテン教授と教授に縁のある方々をお招きしてミニシンポを開催します。アンテンさんは95年から通算3年ほど東北大に在籍しており、様々な研究者と多くの共同研究を行ってきました。このミニシンポでは、みなさんの最近の研究を紹介していただきます。
日時:11月26日13時〜16時
場所:東北大学理学部キャンパス合同C棟N204号室
2015.10.23
恒例の圃場整備でした。

2015.10.14
今年最後の八甲田です。1300mは雪、600m〜1000mは紅葉が見頃でした。
 _
_
 _
_
 _
_
2015.9.25
苫小牧に行ってきました。市道にヒグマが出たというニュースを聞いた次の日でした。

2015.9.14
また八甲田に行ってきました。
 _
_
2015.8.6-10
恒例の八甲田実習でした。
 _
_
 _
_
 _
_
_
2015.7.18
また八甲田に行ってきました。空気が澄んでいました。今年の八甲田は渇水のようで、干上がっている池塘をいくつか見ました。
 _
_
 _
_
 _
_
2015.6.26
生命科学研究科院生会のソフトボール&BBQ大会がありました。今回も植物生態分野と合同で参加です。
 _
_
 _
_
今年はあれよあれよという間に1回戦、2回戦、準決勝と勝ち進み、決勝まで行ってしまいました。 決勝は同点引き分けでしたが、じゃんけん9回勝負で負け、準優勝となりました。
2015.6.16
金華山島に行ってきました。
 _
_
金華山は牡鹿半島の沖に浮かぶ島で、ニホンジカが宗教的な理由で保護されており、植物が強烈な採食圧にさらされている島です。きれいな芝生は人為的に手入れされているのではなく、ニホンジカがきれいに食べ尽くした結果です。
 _
_
こういうところに生育する植物は何らかのかたちで採食圧に適応しています。物理的防御をしているもの、化学的防御をしているもの、あとは食べられても割と平気なものなどです。物理的防御をしている植物のなかには、本土の同一種植物に比べ、防御能力が強くなるような変異をもっているものもあります。
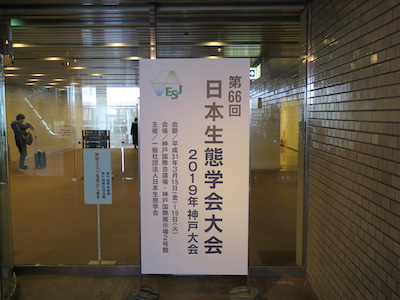 _
_
放置しておくと植生がシカに破壊されかねないため、25年ほど前に防鹿柵が設置されました。Werger et al. (2002) では、採食圧から開放されたあとの植生遷移における光獲得競争の解析をしました。そのときは1994年に防鹿柵内外で層別刈り取りを行い、柵ができてから出現した植物と柵外で旺盛に生きられる植物とでどのような違いがあるかを調べたものです(この論文では彦坂はデータ解析を行いました)。今回は、そのときの柵がどうなっているか、と見に来たのですが、柵は役割を終えて鉄線が外されていました(左写真の右側の木の杭に鉄線がかけられていた)。右の写真は2004年4月に撮影した同じ柵です。ブナが大きくなるなど、当初の目的は果たされた、ということだろうと思います。新たに鉄柵が作られ、植生保護区が拡大されていました。もっとも、金網が破れてシカが入り放題になっている区画もありましたが。
2015.6.12
八甲田の湿原に調査に行ってきました。
 _
_
左は南駒込山湿原とうちわで呼んでいる湿原、右は田茂范岳から見た下毛無岱湿原
 _
_
チングルマの海(田茂范)とワタスゲの海(高田谷地)
 _
_
イワイチョウの長花柱花(めしべが長くておしべが短い)と短花柱花(めしべが短くておしべが長い)。異型花柱性といいます。
2015.4.20
理学部の広報誌Aoba Scientiaで研究室を紹介してもらいました。こちらです。
2015.3.27
卒業式や卒業祝賀会がありました。井上真登さんが東北大学総長賞を受賞しました。
 _
_
2015.3.22
鹿児島で行われた生態学会全国大会に参加してきました。
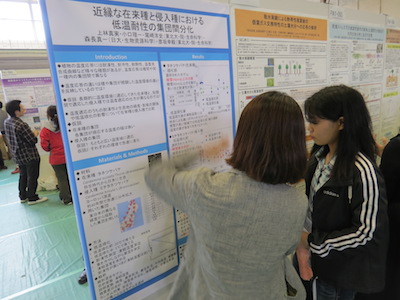 _
_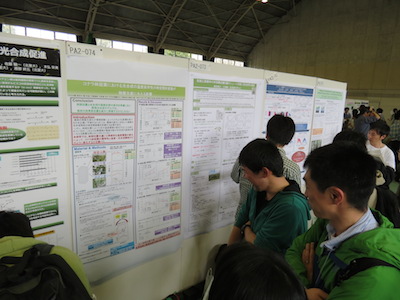
2015.2.12
修論最終審査と修了祝賀会がありました。
 _
_
2014年のトピックスはこちら
2013年のトピックスはこちら
2012年のトピックスはこちら
2011年のトピックスはこちら
2010年のトピックスはこちら