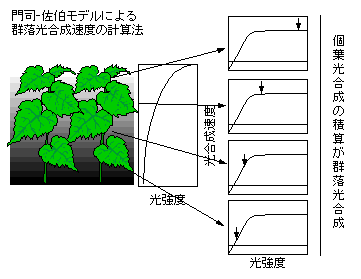
光合成の生理生態学講座
目次
はじめに (200709 15)
葉群光合成速度の計算原理(200709 15)
葉群内の個葉光合成特性(200710 15)
吸光係数と葉面積指数(200711 27)
窒素分配(200712 25・200801 06)
窒素利用を考慮した最適葉面積指数(2009 0115) New
動的な葉群光合成モデル
葉っぱ一枚しかもたない植物、というのもいるにはいますが、多くの植物はたくさんの葉を持ちます。また、だいたいにおいて植物は群落を形成して生活しており、ある一定面積の中にはたくさんの葉があることがわかります。生態系の物質循環を考えるとき、植物の大きな役割の一つは光合成をして、炭素を取り込むことです。光合成をする単位として群落を見ると、群落というのは葉の集まりです。個々の葉の光合成の総和が葉群光合成(群落光合成)ですが、こちらで説明したように、個々の葉の微環境、特に光環境は大きく異なり、それに依存して光合成量は異なります。本項では、葉群光合成を葉の光合成の総和と考えたときに根底を支配する論理を考察します。難しい言い方ですが、葉群光合成に影響を与える要因について知ってもらおう、ということです。
なお、「葉群光合成」はcanopy photosynthesisの訳として出しました。慣習としては「群落光合成」のほうがなじんでいますが、ここで説明するモデルは葉のみを扱い、茎・根などは無視しているので、「葉群光合成」のほうが妥当ということです。
本項を読む前に、こちらを読み、葉群内の光環境の不均一性について理解してください。
葉群を光合成の単位として初めて考えたのはボイセン-イェンセンであろうと思われます(Boysen Jensen 1932. ちなみに「Boysen Jensen」が姓。)。彼はシロガラシなどの小さな鉢植え群落を作り、その光合成速度を測定しました。さらに個葉の光合成速度との比較を行い、葉面積あたりの個葉光合成速度に比べ葉面積あたりの葉群光合成速度が低いことを示し、葉群光合成が個葉光合成の単純な和ではないことを指摘しました。これは、彼自身が考察したように、葉群内の光環境の不均一性など、個葉光合成を測定するときには無視されていた要因が葉群光合成速度に大きな影響を与えるためです。
葉群光合成速度にどのような要因が影響するのか、についての理論的な枠組みはMonsi and Saeki (1953) によって実験的かつ理論的に明らかにされました。彼らはこちらで説明したような葉群内の光環境分布を実測・理論の両面から明らかにし、さらに、個葉の光合成特性と光環境分布を巧みに組み合わせることにより、葉群全体の光合成速度をモデル化することに成功しました。
Monsi and Saeki (1953) の葉群光合成モデル(群落光合成モデル)の原理を簡単に紹介すると以下の通りになります。まず、葉群内には光環境の勾配があります。ある層nの葉が受ける葉面積あたりの光強度IincnをIincn=K Io exp(-K Fn)として計算します(詳しくはこちら)。そして各葉の光ー光合成曲線を仮定します(Monsi and Saeki モデルでは直角双曲線と直線を組み合わせたものが使われた)。Monsi and Saeki モデルでは全ての葉が同じ光ー光合成曲線を持つと仮定し、各層の光強度と光-光合成曲線から、各層の葉の光合成速度を計算しました。そして、全ての葉の光合成速度の積分が葉群光合成速度(群落光合成速度)として計算されたわけです。
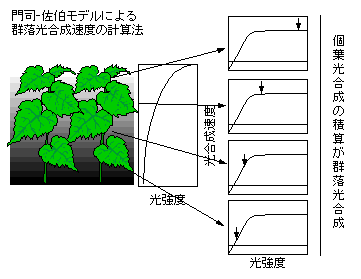
葉群光合成速度は一般に土地面積あたりで表されます。このモデルでは土壌や根・茎の呼吸は無視されており、もっぱら葉の炭素収支のみが計算されます。
Monsi and Saeki (1953) の論文が書かれた当時は戦争直後であることもあり光合成速度を測定するシステムがなく、彼らはボイセン-イェンセンが測定したシロガラシなどの個葉光合成速度を用いて葉群光合成速度を計算し、実測された葉群光合成速度と比較するということをしています。下の図はMonsi and Saeki (1953) に載っている実測・予測された光合成速度の比較です。予測は非常にうまく実測値とあっており、モデルが妥当であることを示唆しています。
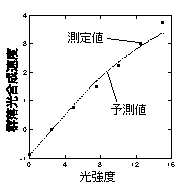
あとで述べますように、葉群光合成モデルにはこのあと様々な改良が施されています。しかし基本−葉群内の光環境と個葉の光-光合成曲線から個葉の光合成が計算され、その和として葉群光合成速度が計算される-は現在も変わっていません。
Monsi and Saeki (1953) のモデルでは、全ての葉が同じ光-光合成曲線を持つことが仮定されていました。この仮定が正しくない、つまり葉によって光合成特性が異なることはすでに彼ら自身が知っており、例えばSaeki (1959) はケイトウの群落内で上部の若い葉の光合成能力(光飽和下の光合成速度)や呼吸速度が下部の年取った葉に比べ高いことを報告しています。彼らが、このような正しくないとわかっている仮定を用いた理由はおそらく二つあります。一つは計算能力の限界です。当時コンピュータなどという便利な機械はまだなく、彼らは計算尺や手回し計算機などで複雑な計算をする必要がありました。計算式はできる限り解析的に解き、解くのが不可能な部分を計算機で補うことをしていたのではないかと思われます。そのため計算を単純化させることは大事な問題であったと想像されます。もう一つは、このような仮定でも葉群光合成速度をかなりの精度で推定することが可能であったからだと思われます。葉群内では下部の葉の光環境は悪いため光合成は光律速であり、光合成能力の差が現れにくいこと、また、上部の葉と下部の葉を比べると、弱光下での光合成速度にはあまり大きな差がないため、上部の葉と同じ性質を仮定しても誤差はあまり大きくならないのです。Saeki (1959) は、葉群光合成速度を推定するためには、葉群最上部の葉の光合成能力と葉群の葉の呼吸速度の平均値がわかれば十分であると述べています。しかし実際には葉群内の個葉の光合成特性には大きな違いがあり、後述するようにそれは植物の資源利用と強く関連があります。
こちらで述べたように、葉群内には光環境に大きなばらつきがあります。多くの場合、個葉の光合成特性は光環境に依存して異なり、例えば上部の葉ほど光合成能力・呼吸速度・窒素含量(葉面積あたり)が高いなど、いわゆる陽葉と陰葉の違いが見られます(Hirose and Werger 1987a,b, 1988)。陽葉と陰葉については詳細をこちらに書きましたのでご覧ください。
ただし、葉群内の上部-下部の光合成特性の違いは、全て陽葉-陰葉の違いと同じであるわけではありません。草本群落では、多くの植物が上部に葉を展開します。ある時期に若く最上部にあった葉は、新しい葉が上部に展開されるたびに被陰によって光環境が悪くなっていきます。このようなケースでは、下部の葉といえど葉が作られたときは光環境が良かったため、葉は強光で高い光合成速度を実現できるよう厚くなっています。葉の形態は一度できてしまうとあまり変わらないため、下部の葉でも上部の葉と同様厚いことになります(Hirose et al. 1988)。一方、森林では植物の成長はそれほど速くなく、葉の光環境はあまり変化しません。このため、上部の葉は厚く下部の葉は薄いという陽葉-陰葉の違いが見られます(Ellsworth and Reich 1993)。森林樹木の葉群内の個葉の性質については多くの研究があり、特にエストニアのUlo Niinemetsが精力的に研究を行いました。多すぎてここでは紹介しきれないので最近出たレビューを示しておきます(Niinemets and Valladares 2004, Niinemets 2007)。
葉群光合成速度には様々な要因が影響します。Monsi-Saeki モデルを使った初期の研究では、主として葉群構造に着目し、吸光係数と葉面積指数が葉群光合成速度に与える影響が研究されました。この過程で生まれた概念が最適葉面積指数です。葉の光合成速度は、弱い光ほど低くなり、ある光強度(光補償点)よりも低いと呼吸速度が光合成速度を上回るようになります。Beerの法則に従えば、群落の最下部の葉が受ける光強度は群落が持つ葉面積指数が多いほど低くなります。葉が受ける光強度がプラスのCO2吸収を維持できないくらい低いと、その葉は光合成生産には役に立ちません。Monsi-Saekiモデルにしたがえば、最下層の葉がぎりぎりプラスのCO2吸収を維持できる程度に葉面積指数を持てば、その群落の光合成量が最大になり、それ以上葉を持つと、かえって群落光合成は低くなります。群落光合成を最大にする葉面積を「最適葉面積指数」と呼びます。
最適葉面積指数は葉の光合成特性(光補償点-光合成速度が0になる光強度)と吸光係数に依存します。全ての葉の光合成特性を一定にした場合、葉面積指数と群落光合成の関係は以下のようになります。
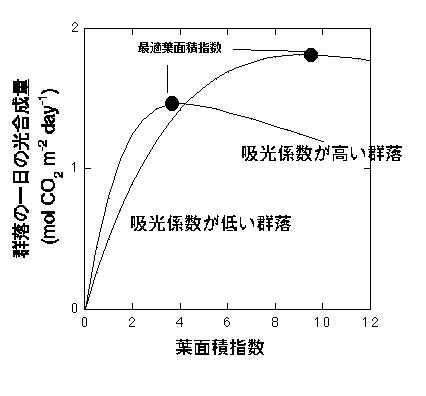
葉群光合成速度と要面積指数の関係。昔ある本の章を書くために計算したものの長くなってしまうためボツになった計算。こちらに示したヌマガヤとオオオナモミ群落のデータをもとに計算したものですが、詳細は忘れました。
図にあるように、最適葉面積指数は吸光係数が高くなると低くなります。これは吸光係数が低いと葉群の下部へ届く光が少なくなり、葉面積指数が低くとも光補償点を下回ってしまうためです。また、最適葉面積指数が実現されている場合、葉群光合成速度は吸光係数が高い群落ほど高くなります。最適葉面積数が実現されている状態では、葉群が吸収する光の量は一定です(最下部の葉が吸収する光が光補償点)。つまり、同じ光を吸収しているのに吸光係数が高い葉群のほうが光合成速度が高いのです。これがなぜかというのは少し難しいですが、理屈は以下の通りです。まず、吸光係数が低い葉群に比べ、吸光係数が高い葉群では、最上部の葉が吸収する光が強くなります(こちら参照)。しかし、ご存じの通り光合成速度はあまり光が強いと飽和し、光強度に依存しなくなります。つまり最上部の葉の光合成量は、もともと光が強いため葉の角度に大きな影響を受けません。一方、下部の葉の光合成速度は、葉の角度に大きな影響を受けます。吸光係数が高い群落では下部にもれる光が少ないため光合成量が少ないのに対し、吸光係数が低い群落では光合成量が多くなります。この差が葉群光合成速度にひびき、吸光係数が低い群落のほうが光合成量が多くなります。要するに、吸光係数が高いと群落光合成の最大値が低いのは、最上部の葉は強い光を吸収できるものの、全ての光を利用できるわけではない(光合成が頭打ちになっている)ので、同じ光量を吸収しても、無駄が多いからです。
最適葉面積指数の存在については、様々な議論があったようです。実験的には、吸光係数の異なる種を使って様々な密度の群落を作ったり(Watson & Wats 1959)、イネの葉に重りをつけて葉の角度を調節し、吸光係数の異なる群落を人為的に作ったり(Tanaka 1972; Monsi et al. 1973)して、上記のような群落光合成-葉面積指数関係を実測した例があります。一方、理論的な面から最適葉面積指数を否定した議論もありました。McCreeは、群落下部の葉ほど光合成の光補償点が低いことを指摘しました。Monsi-Saekiモデルでは、群落の全ての葉が同じ光合成特性を持つと仮定していますが、現実は上に書いたとおり、群落下部の葉ほど呼吸速度が低いという特性があります。最適葉面積指数がなくなるかどうかは別として、呼吸速度の変化を入れると最適葉面積指数の値が大きく変わるのは確かです。ここまでの議論は60-70年代にかけて行われたものです(黒岩先生の教科書に詳しいいきさつが載っています)。これらの問題はほとんど忘れられていたといっていいと思われますが、80年代になって、新たな問題が出てきました。それが、群落が持つ窒素の問題です。
上で述べたように、光合成特性には葉群内で違いがありますが、Monsi&Saekiモデル以降、多くの葉群光合成モデルでは無視されてきました(例えばJohnson and Thornley 1984)。
一方、葉群光合成の分野とは別に、光合成特性の種間差や環境応答を進化生態学的(物質経済的)観点から理解しようという試みが70年代後半から始まりました。これがこちらで紹介したコスト−ベネフィット解析です(Mooney and Gulmon 1979, 1982)。この考え方から、光合成を利得、窒素をコストとみなす考え方が発展します。この仮説は例えばGulmon & Chu (1981)やDeJong & Doyle (1985)などが光環境と窒素含量の相関を示すことにより支持されていきました。さらに、Mooneyのグループの一員であるField (1983) は、個体の光合成を最大化する窒素分配について考察しました。光合成と窒素含量の間に関数関係があるとすると、理論的には、個体内の窒素を一定としたとき、個体の光合成量は、個体内の全ての葉が以下の式を満たすように窒素を分配すれば最大になります。
λ= ∂A/∂N=一定
ここで、AとNは個葉の光合成量と窒素含量です。ラムダはラグランジェの乗数で、定数です。これを図を使って説明しましょう。
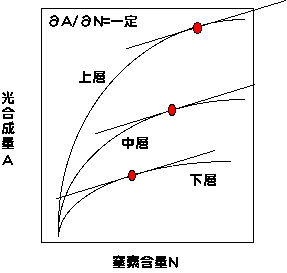
話を簡単にするために、葉群が3層からなると考えましょう。そして、各層における窒素含量と光合成量の関係を推定します。こちらで述べましたように、窒素含量が増えると光合成能力が上がります。このため窒素が増えると光合成量が上がります。注意しなければいけないのは、層によって光条件が違うため、同じ窒素含量でも層によって光合成量が異なることです。下層の葉は弱い光しか受けませんが、弱光下の光合成速度は窒素を増やしてもそれほど変化がなく、同じ窒素含量では、窒素量増加に対する光合成量の増加(∂A/∂N)が小さくなります。しかし下層の葉でも窒素含量が低いと∂A/∂Nが上がります。つまりλを一定にするということは、上層に多く、下層に少なく窒素を分配することになります。図中の赤丸がλを一定にする点です。各葉にこのように窒素を分配すると、葉群光合成速度が最大になります。注意しなければいけないのは、最適分配は葉群がもっている窒素量に依存するということです。葉群がより多くの窒素を持っていれば、赤丸は全体的に右にずれます(λが小さくなる)。
上の話はかなり高等な数学で、私にもきちんと理解できているわけではありません。そこで、直観的に理解するために以下の思考実験をしましょう。
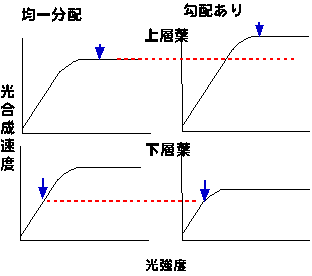
今度はもっと単純に、二層からなる葉群を考えます。左側の葉群では上下層とも等量の窒素をもつとします(均一分配)。一方右側の葉群では窒素を上層に多く下層に少なくもちます(勾配あり)。このとき葉群全体の光合成量はどうなるでしょうか。詳しくはここでは説明しませんが、弱光下の光合成速度は窒素含量が変わってもあまり変わりません。このため、左右どちらの葉群とも下層の葉の光合成量はそれほど変わりません。一方、上層葉は強い光を受けます。強光下の光合成速度は窒素含量が高くなれば高くなりますので、右の葉群の葉のほうが光合成速度が高くなります。結果として、下層の光合成量が大して変わらないのに上層の光合成量が異なるため、勾配がある葉群のほうが光合成量が多くなります。
つまり窒素分配理論の概要は以下の通りです:弱光では、光合成速度が光に律速されるため、窒素含量を高くして最大光合成速度が高い葉を作っても実際の光合成量は上がらない。それくらいなら、強い光が当たる葉に窒素をまわしたほうが、たとえ個葉の光合成速度が低くなったとしても、個体の光合成速度は増加する、というわけです。
Field (1983) は上記の理論(ラグランジェ乗数を使った方)をもとに、低木の葉群を使って実際の窒素分配と、最適な窒素分配を計算し、窒素分配の一日の光合成速度に対する影響を調べました。結果は、光条件が高い葉ほど窒素含量が高かったものの、窒素を均一に分配・実際の分配・最適な分配をしたときの個体の光合成速度をそれぞれ計算してみてもあまり違いがない、という、あまりエキサイティングではない話になってしまいました。なお、Fieldは個体の全部の葉っぱを調べたわけではなく、一つの株の中の5枚(!)の葉っぱについて調べただけで、実際の個体の光合成を計算したわけでもありません。
MooneyやFieldの理論を葉群光合成の理論に融合したのがHirose & Werger (1987b) の仕事です。彼らは、まず、光-光合成曲線を非直角双曲線で近似しました(非直角双曲線についてはこちら)。次に各葉の被直角双曲線の4つのパラメータ飽和下の最大光合成速度Pmax、初期勾配f、曲線の凸度q、呼吸速度Rを葉窒素含量の関数で表しました(Hirose & Werger 1987)。彼らのデータのかわりに、私が使ったものを下の図に示します。
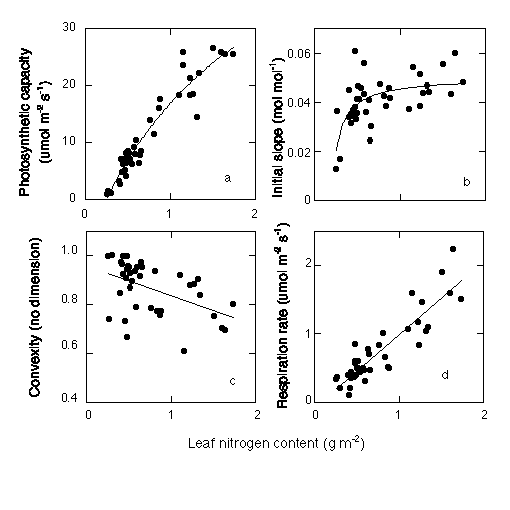
窒素含量leaf nitrogen contentとPmax (photosynthetic capacity)、f (initial slope)、q (convexity)、R (respiration rate)の関係。オオオナモミのデータ。うちの研究室の修士課程を卒業した須藤君がとったものです。
ここでは回帰式をいちいち示しませんが、これらの回帰式を組み合わせると一枚の葉の光−光合成曲線を窒素含量の関数として表すことができます。次に、層別刈り取りを行います。これまでの群落光合成の研究では、群落の葉群を高さ別に分け、葉面積と重さを測るだけでしたが、彼らは窒素含量も測定しました。これで各層にどれだけ窒素があるかわかります。Beerの法則を使えば各層の光環境もわかるので、窒素含量と光環境から、各層の光合成量を計算することができるわけです。以下はセイタカアワダチソウ群落で得られた積算葉面積指数と窒素含量の関係です。
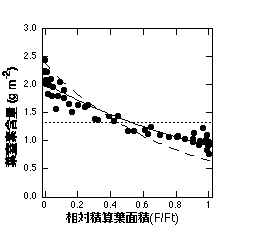
セイタカアワダチソウ群落内の窒素分配。横軸は群落上部から積算した葉面積を群落の総葉面積で除したもので、0が群落最上部。●が実際に観察されたデータ、実線がN = N0 exp(-KN F/Ft)でフィットしたもの、点線が窒素含量の平均値、破線は理論的に求められた最適な分配。彦坂(1998)を書くときに広瀬さんから生データをもらって描いたものです。
Hirose & Werger (1987b) では、葉群光合成を計算するだけでなく、「もし各層への窒素分配が変わったら」という思考実験(シミュレーション)を行いました。葉群が持つ窒素量を一定とし、各層の窒素含量が一定だったら、あるいは窒素含量の勾配を現実よりも急にしてみたら葉群光合成速度がどのように変わるかを計算してみたわけです。その結果、彼らが研究に用いたセイタカアワダチソウ群落では、もし窒素分配に勾配がない場合(窒素含量一定)に比べ、実際の葉群の光合成速度は20%以上高いことがわかり、窒素分配の勾配に大きな意味があることがわかりました。また、最適な葉群と比べると、窒素勾配は実際の勾配に比べやや急でした(上の図破線)。しかし、最適な場合と比べ現実の葉群の光合成速度は10%以下の違いしかなく、現実の葉群は最適に近い分配を実現していることがわかりました。これはField (1983) の結果とは対照的ですが、Fieldの仕事では、明るい場所に生えている低木を使いましたので、個体内の光環境の違いが小さかった(下の葉でもあまり暗くなかった)からではないかと思われます。
では最適な窒素分配とはどのような分配でしょうか。Farquhar (1989)は、最適な分配は、各層の受光量とPmax(飽和光下の最大光合成速度)が比例するときに葉群光合成速度が最適になると指摘しました。
I'1:I'2:I'3... = Pmax1:Pmax2:Pmax3...
ここでI'は受光強度を、下付の数字は層の番号を意味します。ここから最適な窒素分配を計算できます。Anten et al. (1995a) は、Pmaxと窒素含量(Narea)がPmax=a(Narea-b)と(aは傾き、bはx切片)直線の関係にあるとき、最適な窒素分配は以下のようになることを示しました。
Narea - b = (NT-bFT) K exp(-KF)/(1-exp(-KFT))
ここでNTは葉群全体の窒素含量(土地面積あたり)、Kは吸光係数、Fは積算葉面積指数、FTは総葉面積指数です。ただし、この式が成り立つにはいくつか条件があり、初期勾配fや曲線の凸度qが一定であること、窒素含量と呼吸速度Rが比例しているなどが必要です。ややこしい式ですが、こちらに書いたように、K exp(-KF)が層の受光量を意味します。(NT-bFT)/(1-exp(-KFT))は定数なので、Narea - bは受光量と比例することになります。Pmax=a(Narea-b)ですから、要は、上にも書いたように受光量とPmaxが比例するように窒素を分配することが最適だということです。どうしてこうなるか、数学的な証明は原著をご覧ください。
さて、この式により、最適な窒素分配を比較的簡単に計算できるようになりました(それまではシミュレーションで数値計算しないと最適分配が出なかったのです。Hikosaka and Hirose 1997では苦労しました)。現実の窒素分配は最適分配からどれだけ離れているのでしょうか。Anten et al. (1995) では以下の式で窒素分配を回帰し、回帰係数KNを得ました。
Narea - b = (NT-bFT) KN exp(-KNF)/(1-exp(-KNFT))
この式はKがKNに変わっただけです。つまりKNとKが等しければ最適ということになります。で、様々な葉群のKNとKを比べてみると、KNとKの間には高い相関がありましたが、数字を見ると、KNはKの半分程度でした(Anten et al. 2000)。つまり現実の分配は最適な分配よりもかなり緩やかであるということです。窒素分配が常に最適より緩やかであることは意味がありそうです。勾配を急にするということは最上部の窒素含量を異常に高めることになりますが、これは植食者に有利であるので植物にとっては不利である(Stockhoff 1994)、という考え方がありますが、実際のところはまだよくわかっていません。
上では窒素を考慮していない状態での最適葉面積指数の話をしました。光合成に対する窒素の役割を考えると、どの葉面積が最適かが変わってきます。
窒素と「最適葉面積指数」の関係においては、窒素が有限の資源であることということが最も重要な問題です。土壌の窒素栄養が植物の生育を律速することは、農業においても自然界においてもよくあることです。群落(個体)が持つ窒素が限られていると考えましょう。窒素が少ないのにたくさんの葉面積を持つと、個々の葉の面積あたりの窒素濃度が下がります。そうすると、個々の葉のPmaxが低くなり、強い光が当たってもたいして光合成できない、という状態になります。逆に葉面積あたりの窒素濃度を上げるために葉面積を減らしすぎると、葉が少ないために光を充分吸収できなくなります(下図)。ということで、葉群が窒素をどれだけ持っているかで最適な葉面積指数が異なり、同じ吸光係数でも持っている窒素が少ないほど最適葉面積指数が下がります(Anten et al. 1995b)。
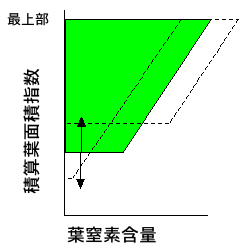
この他、どちらかというと細かい問題なのであまり指摘されることはありませんが、窒素を考慮すると吸光係数と最適葉面積指数の関係ががらっとかわります。Monsi-Saekiモデルでは葉のPmaxを一定にしていました。そのため、吸光係数が大きい葉では、受光量が高いわりに光合成速度が低く、光を吸収しても光合成に使えない、という状態になってしまいました。このため、葉面積を最適化したときの光合成速度が吸光係数が大きいほど低くなるわけです。しかし、窒素分配を考慮し、上部の葉にたくさん窒素を分配できるとなると話は違います。強い光を受ける葉は高いPmaxを持つわけです。仮に、受光量とPmaxを完全に比例関係におけるとすると、Monsi-Saekiモデルであったような無駄は全くなくなり、群落光合成速度は群落の光吸収量に比例することになります。同じ葉面積指数(最適葉面積指数より低い場合)で比較すると、群落光合成速度は吸光係数が高いほど高くなります。これはMonsi-Saekiモデルでも同じ結果ですが、最適葉面積指数における群落光合成速度は異なり、吸光係数が高いほど高いという結果がでます(Anten et al. 1995b)。
しかし、これは個葉の窒素含量がどこまでも高くなれることを仮定した場合です。そのような「理想的な」窒素分配にすると、最上部の葉の窒素濃度は300 mmol N m-2 とかいうあまり現実的ではない値を持つことになります(Anten et al. 1995a. 彼は、全くあり得ない値ではない、と主張してますが)。実際には、現実の群落の窒素分配は数学的に導かれる最適な分配とは違います。また、Anten et al.のモデルでは、窒素含量とPmaxの関係を直線としていますが、生理学的に見ても、窒素を増やせばPmaxは際限なく上がるか、というと、そうとも思えません。CO2拡散の問題などもあり、ある程度窒素含量が増えるとPmaxの増えは頭打ちになると思われます。現実に、いくつかの種では窒素含量とPmaxの関係が頭打ちになります(上の図参照)。この2点から、やはり葉群の最大光合成速度は吸光係数が低いほうが高い、というのが現実的だと思います。
窒素含量とPmaxの間の相関が飽和型の曲線(頭打ち)であると仮定すると、最適な分配や葉面積指数が、現実の葉群とそう変わらない値になります。下の図はHikosaka & Hirose (1997) に載せ損なったもの(正しくない図が載っています)です。
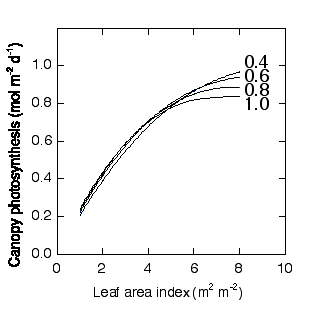
縦軸が葉群光合成速度、横軸が葉面積指数、図中の数字は葉群の吸光係数(K)を示します。
ここでは、群落の窒素量を一定にするのではなく、群落の平均葉窒素含量が一定になるという仮定をおいています。窒素分配は最適化されています。ここで使っている窒素と光合成の関係はHirose & Werger (1987a) によるセイタカアワダチソウのデータです。ここでは窒素含量とPmaxの間は直線であると仮定されていますが、曲線の凸度(q)が高窒素含量ほど下がるという仮定がおかれています。この仮定は、実質上窒素とPmaxの関係が曲線であることと同じ意味を持ちます。こういった仮定をおくと、群落光合成速度の最大値は吸光係数が高いほど低くなります。
また、Hirose et al. (1997) では、群落窒素量・葉面積指数・群落光合成速度の関係をシミュレーションで調べました。このシミュレーションによってわかったことは、最適な群落窒素量があるということです。葉呼吸速度と葉窒素含量が比例するという仮定をおいているので、群落の窒素量が多すぎるとかえって群落光合成速度が低くなるわけです。
なお、窒素を考慮に入れた場合は、最下層の葉の光補償点はほとんど問題にはならなくなります。現在使われている群落光合成モデルでは、個葉の呼吸速度は窒素含量と正の相関を持ちます。こういう仮定をおくと、最下層の窒素含量を下げて呼吸速度を下げると、それと同じ分だけ上層の葉の呼吸速度が上がります。したがって、群落の呼吸速度は群落の持つ窒素量に依存することになり、個葉の呼吸速度を考える必要がなくなるわけです(Anten et al. 1995)。